
正直なところ、CRO時代の私は依頼者に対して思うところがあり過ぎてモヤモヤすることも日常茶飯事でした。
そんな私は、CRO時代に感じた依頼者に対する様々な不満をノートに記録していたのですが、今回はそのノートに書き記した不満に依頼者の立場から回答していこうと思います。
第1弾ということで、テーマは「PRTや手順書に書いていない逸脱」です。
 のりす
のりす 製薬業界でかれこれ10年以上働いています。X(旧Twitter)でのフォロワー数は6,300人程。日々患者さんのためにやりがいのある充実したお仕事に取り組んでいます!
過去の自分(CRO)から今の自分(依頼者)に物申す
から今の自分(依頼者)に物申す.jpg)
1997年にCROの存在が法的に定義されてから約28年が経過しました。
今やCROは、医薬品開発や医療機器開発をしていくうえで欠かせない存在となっていますよね。
CRO側の経験やノウハウの蓄積や積極的な業界活動への参加を経て、ただの「委受託業者」に留まらず「開発パートナー」としての地位を確立したと言えるでしょう。
しかしながら、担当者レベルで見ていくとCROと依頼者の隔たりは依然として存在しているのも事実です。
この記事を読んでいるCROの方々の中でも依頼者に対する不満を感じている方がいるのではないでしょうか?(逆も然りですが…)
この課題は学会や勉強会などでも数多く議論されてきていますが、所属会社を公表しての発言であることやCROから依頼者への発言などは若干躊躇してしまい本音を抑えながらの議論になってしまっているようにも感じます。
冷静沈着に議論することも非常に重要ですが、本質的な解決を目指すためには時にはぶつかり合いながら議論をしていくことも重要ではないでしょうか?
そこで、今回は私がCRO時代に依頼者への不満を書き綴ったメモに現在は依頼者の立場になっている私が回答していこうと思います。
 のりす
のりす 自分から自分に対するメッセージなので本音で容赦なく回答していきます。そのため、心臓が弱い方は閲覧をお気を付け下さいませ…笑
「CRO時代の私」vs「依頼者時代の私」のやり取りからCROと依頼者の相互理解に繋がるきっかけが生まれることを祈っています。
CRO時代の私が感じていた不満~逸脱編~

CRO時代に依頼者に対して抱いた不満は色々あるのですが、今回の記事では”PRTや手順書にはっきり記載していないのに逸脱にされた”というモヤモヤについてお話していきたいと思います。
CROのりすの不満
CRAになったからにはプロトコールや手順書を読み込むのは当たり前ですが、プロトコールや手順書に明記されていないにも関わらず「それは逸脱に該当します」と依頼者見解が伝えられた時には不満爆発でしたね。
 のりす
のりす 「それを施設に言うのは私ですが?依頼者さんが説明しに言って下さいよ」と言いたいくらいでした。
その類のお話を先生やCRCさんに話すのはCRAだし、怒られるのが分かり切っているのにひどい…というお話ですね。このあたり、どう説明してもらえますか、依頼者のりすさん?
そもそも細かい手順全てが記載されていることがどこまで重要なのか(依頼者のりす)
被験者さんの安全性やデータの信頼性に影響を及ぼすような重要な手順が漏れているのは論外だけど、それ以外の細かい部分については漏れていたとしてもさほど重要だとは思わないというのが本音。
細かい部分の記載漏れ・定義漏れはリスクとして想定できるけども、それが与えるインパクトは軽微だと評価しているということだね。
つまり、軽微な逸脱は承認取得には影響を及ぼさないので、そこに目くじらを立てて怒ること自体に疑問を感じるところ。
GCP第1条にも以下のように書いてあるよね。
第一条 この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第三項及び第十二項(同条第十五項及び法第十九条の二第五項において準用する場合並びに法第十四条の二の二第五項(法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項(これらの規定を法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち医薬品の臨床試験の実施に係るもの並びに法第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
治験を実施するときに重要なことは、以下の3点。
- 被験者の人権が保護されていること
- 安全の保持及び福祉の向上が図られていること
- 治験の科学的な質及び信頼性が確保されていること
上の3つに該当しないような軽微な逸脱についても過敏に反応することはGCPで求めていることでも無いので、当然、薬事承認に影響を及ぼすとも考えにくい。
それに、プロトコールを作る立場になると分かるけど、あらゆるパターンを想定して細かな部分まで漏れなく始めからプロトコルや手順書に反映するのはかなり難しい。
では問おう。CROのりす君はなぜそこまでそのことが不満なのかな?
依頼者のりすは、承認取得に影響があるか無いかに重きに置いている点に注目
今回の件を不満だと感じる理由(CROのりす)
私がCRO時代に不満と感じた理由は概ね以下のような理由。
- 施設に伝えたら怒られるのは自分だから(依頼者が説明に行ってくれ)
- 上長や依頼者から怒られた時に理不尽と感じたから
- 業務評価に「逸脱件数●件以下に抑える」などを入れていたから
逆に言えば、PRTや手順書に書いていないことで逸脱と施設に伝えても施設から何も言われずに自分の評価も特に落ちないのであれば不満に思っていなかったかもしれない。
承認取得への影響よりも実務的な影響に重きを置いている点に注目
1~3に対する見解(依頼者のりす)
1については後述。
2は、承認取得にも影響を及ぼさないようなインパクトの小さい逸脱であるにも関わらず怒るのは、その上長や依頼者の担当者の勉強不足だと思う。
そんな上長や依頼者がいるならQMSの講習を受けることをおすすめしたい。
3は、当時私がCROにいた頃はQMSが浸透していなかったからかもしれない…「逸脱」といっても重さにはグラデーションがあるので一律にしてCRAの評価指標にするのは不適切だと思う。
施設側にも事情がある(依頼者のりす)
PRTや手順書に明記されていないことで軽微な逸脱とされたときにどのように思うのかを院内CRCさんとSMOのCRCさんのそれぞれからお話を伺ったことがあるので紹介するね。
あくまで一例として。
院内CRCさんから聞いたお話
お話を聞いた院内CRCさんによると、施設スタッフに迷惑がかかることがあることや逸脱報告時の院内フロー(書式作成など)が非常に負荷がかかることなどがあるとのこと。
SMOのCRCさんよりはあまり気にしない方が多いかもしれないけど、「しっかり書いとけ!」とは思うとのことでした。
SMOのCRCさんから聞いたお話
立場的に施設の方々(PI、SI、院内CRCさん、院内スタッフなど)への報告に精神的な負荷もかかるとのこと。
PRTや手順書に書いてないので自分が悪くないのに、逸脱ということを伝えることで円滑なコミュニケーションに支障が出ることもあるとのこと。
依頼者の立場で感じたこと
PRTや手順書にしっかり書ききることができなかったのはもちろん依頼者側の責任だと思います。
一方で、医薬品開発で何より大切なのはGCP第1条に書かれているような被験者さんの人権・安全性確保や試験データの信頼性の担保だとも思っています。
なので、軽微な逸脱についてはステークホルダー全体での意識改革が必要なのかもしれません。
QMSの考え方も大分広がってきていますが、CTQ要因等について深く理解できていない方々も多い気がしています。
Risk AcceptanceやMitigationの本質的な意味は?Fit for purposeは意識していますか?
この辺りを大半の方がサラッと説明できるようになったときに治験の現場も今とは違った世界になっているのだと思います。
 のりす
のりす もう少しでGCP Renovationがやってきますからね!!!
正論を言ってまとめようとしているけどちょっと待った(CROのりす)
いやいや、ちょっと待ってくれ!
依頼者の立場からしたら「承認取得に影響が無ければ別にそこまで気にしなくても良いでしょ」的な感じかもしれないけど、現場でやっている身としては心情的な面も重要だったりするのでそこも忘れないでほしい。
例えば、PRTにしっかり書いていないのに逸脱ですとか言われると正直こちらがやらかしたみたいな印象を受けるので良い気分ではないよね?
PRTや手順書にしっかり書いていないのは依頼者側の責任だと思うし、施設にも「承認に関係ないので気にしないで下さい」と伝えても正直モヤモヤすると思う。
依頼者側の視点と現場側の視点は違うので、「承認に関係ないからOKとかそういうことではないのだけど…」と感じてしまうことに注意してほしい。
なので、依頼者側にも真摯な姿勢は忘れないで欲しい。同じ内容でも伝え方が違えば印象も変わるので。
 のりす
のりす あとは、依頼者にはそれが本当に逸脱に該当するのか納得感がある説明をしてほしいと思っていました。「そもそも、それは本当に逸脱なの?」と思うことも多々あったので、しっかりと納得できる理由も説明してほしいところ。
まとめ
この問題については立場の違いによって目的も違うので感覚のすれ違いなどもトラブルの要因のように感じました。
実際にCROのりすの時には、薬事承認申請後にどのような照会事項が来るのか、信頼性調査でどのようなことを確認されるのか、どのようなレベル感で指摘が入るのか等のイメージができていませんでした。
依頼者としては最も気にしている部分なわけですが、それを知らなかったということですね。
CROで経験できる機会はほぼ無いので知らなくてもしょうがないような気もしますが、相互理解のためにはそのあたりも知っておくとより円滑なコミュニケーションが築けたのかもしれません。
一方で、CRAをやったことがなければPRTや手順書に明記されていないのに逸脱とされてしまうことへの不満や怒りも理解できなかったでしょう。
実際にお互いの職場に行ってみて体験するのがベストですがそれもなかなか難しいので、そういう時こそXなどのSNSを活用して相互理解を深めていくのが良いのでしょうね。
審査報告書にはCRA/CRCさんのお仕事の結果が以下のように書かれることになります。
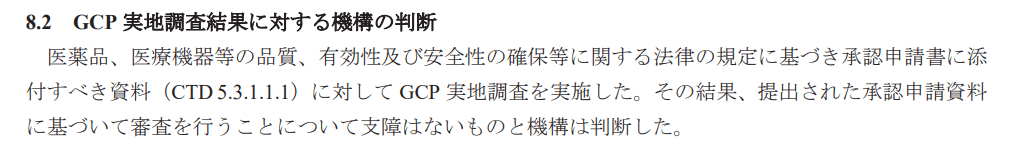
行数にしたらたった3行なのですが、この3行が記載されるために並々ならぬ努力と苦労があるのですよね。
次回は、施設選定や症例進捗管理などの不満について触れていこうと思います。






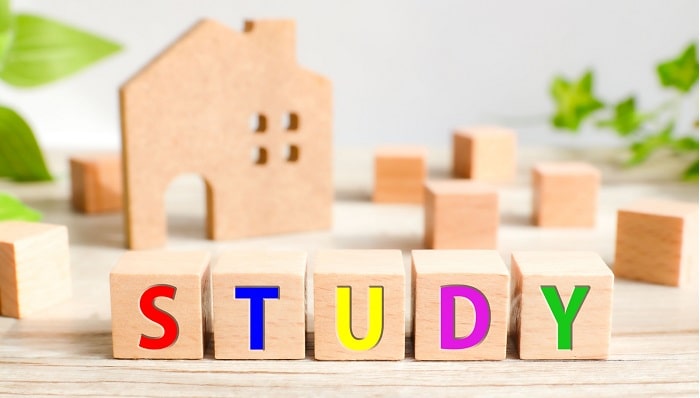
“CRO時代の自分からのメッセージ~ここが変だよ依頼者さん①~” への1件のフィードバック