
CRO時代に依頼者に対して感じた「なんで」について、今回は「なんで依頼者はこの施設を選んだのよ」という疑問をぶつけてみようと思います。
 のりす
のりす 製薬業界でかれこれ10年以上働いています。X(旧Twitter)でのフォロワー数は6,500人程。日々患者さんのためにやりがいのある充実したお仕事に取り組んでいます!
今回のテーマは「治験実施医療機関」

前回のCRO時代の自分からのメッセージ~ここが変だよ依頼者さん①~では、プロトコルや手順書にしっかり明記されていないのに逸脱にされてしまった不満をぶつけていきました。
今回は第2弾として、「なんで症例がほとんど入らない施設を依頼者は選定してるの!?」という不満をぶつけていこうと思います。
当ブログは就活生や経験が浅いCRAやCRCさんにも読んでいただいているので、まずは簡単な前情報からお話していきましょう。
治験実施医療機関の選び方
2024年7月末のデータによると日本には約8,000の病院と約10万の診療所があるそうです。
その中で治験ができるだけの環境が整っている施設となるぐっと少なくはなりますが、それでも非常に多くの施設があることに変わりはありません。
その大量の施設の中からどこで治験をやるか決めるわけですが、決め方にはとても大雑把に分類すると2種類あります。
依頼者が選ぶパターン
1つ目は、依頼者である製薬会社の中でどこで治験をやるのかを決めているパターンです。
CROに委託する場合であっても、依頼者の中である程度施設が決まっている場合は「この10施設でやります」とCRO側に伝えてGCP上の選定を進めてもらうパターンということですね。
 のりす
のりす これが不安ポイントでしてね。
CRO側の立場からすると「絶対ここ症例入らないだろう」とか「こんなやりにくい施設をなぜ選んだし!?」と思うことも多々あるのですよね。
依頼者の中で実施施設が決まっていたらCRO側としてはほぼその施設でやるという選択肢しか取れないのですよね。
CROが選ぶパターン
2つ目は、依頼者が施設を決めていなくてCROにいい感じの施設を選んでもらうパターンです。
依頼者から「いい感じの施設を調査して選んで下さい」というパターンもあって、この場合はCROからSMOに調査依頼をかけて施設を選定したりということもやります。
シミックやイーピーエス等は同じグループ会社にSMOがあるので調査依頼を出しやすい環境があるので、そこを売りにしていることもありますね。
 のりす
のりす 同じグループ会社だからCRAとCRCさんが仲良さそうだと思う方もいるかもしれませんが…そこはね、別会社だからね、えっとね…(誰かが来たようだ…)
CROが施設を選ぶパターンでは、CRO側から提案できる分、依頼者に施設をすべて決められてしまうよりもやりやすい施設を選べるのでCRAとしてはこちらの方が嬉しいことが多いです。
レアですが、施設の方が選定に選んでもらえるようCROに訪問をしてアピールしている姿も見かけますよ。
2つのパターンをお話しましたが、今回の記事の不満は「依頼者が施設を選ぶパターン」の方になります。
CRO時代の私が感じていた不満~施設選定編~

さてさて、当時依頼者が施設を指定してきたのでそれに応じる形で施設を担当していたCROのりすですが…
依頼者が選んできた施設が全然症例が入らないうえに症例が入らないのはCRAにも原因があると言われ不満ムンムンだったわけですね。
さて、このあたりの不満を依頼者のりすにぶつけていくとしましょう!
CROのりすの不満
CRAになると、施設の症例組み入れ状況というのが逐一確認されるわけですが、予定通りに進捗をしていないと原因や対策を求められてそれが過度になるとストレスを感じ不満が爆発することも。
 のりす
のりす 私に「まだ症例が入らないのか」、「いつ症例が入るのか」と言われても、そもそも施設に対象の症例がいなければ入らない。無いものを出せと言われても困る…
というか、この施設選んだの依頼者さんですよね?施設の選び方とか間違ってたんじゃないですか?このあたり、どう説明してもらえますか、依頼者のりすさん?
依頼者での施設の選び方(依頼者のりす)
依頼者がどこの施設で治験をやるかを決める方法は会社によって色々あると思うので、あくまで一例として紹介をしよう。
それを知ることによってなぜこのような状況になっているのかの理解が進むはず。
市販後の販売戦略を考えている
Clinical Operationの視点から見たら治験の施設は”施設対応がやりやすくて症例がたくさん入る施設が良い”となるわけだけど、製薬会社の中には色々な立場の人たちがいるんだよ。
例えば、マーケや営業の視点は治験が終わって上市後の戦略も見据えているわけなので治験の施設はなるべく上市後に戦略を進めやすい施設を選んでおきたいという考え方もある。
良いことなのか悪いことなのかはまた別で議論するとして、上市後に戦略的に販売を広げていくためには関連学会の協力やKOLの先生方との連携は非常に重要で、いわば政治的な立ち回りも重要になるのだよね。
なので、「施設対応のやりやすさ」や「症例がたくさん入る」といった要素よりも、治験以外での戦略的な理由によって施設が選ばれるということもあるということ。
 のりす
のりす 各ステークホルダーによって重視する視点や考え方が違うのは当たり前のこと。
臨床開発部としては治験を早期に完了させることも大事なミッションなので、それを達成するためには多少意見が衝突しようとも他部署と調整をする必要があると思っています。
それができないでYESマンになると…しわ寄せがCROのりす君のところに達するということですね。
施設や先生との関係性もある
ローカル試験の場合は、プロトコルを作成する時にその領域のKOLの先生にアドバイスをもらいに行くこともあり、更に治験をやるとしたらどこの施設がおすすめかを聞いてそこから実施施設の候補を決めていくというやり方もある。
その場合は、先生間の関係性や施設間の関係性が加味されることもあるのだけど、KOLの先生がおすすめしてくる施設で症例がしっかり入るかというそうでもないことも多々…
でも、先生間の関係性を考えて「○○先生には話を通しておいた方が良い」となってこれまた厄介なのだよね。
 のりす
のりす 当然ほとんどの先生はおすすめする施設で治験が進めやすいかどうかなんて知らないですからね。
色々大変なのは分かったけど正直そのあたりは知らんがな…という気持ち(CROのりす)
つまり、上市後の戦略的な理由や先生間の関係性を加味して施設が選ばれることがあるので必ずしも症例がたくさん入ることを見込んで選ばれていないということだね。
正直CROにいると先生間の関係性を把握するまでは至難の業だし、そのあたりのことを考えるのは無理(というか、CRAとしてはそこまで把握する必要もないと思っている)。
色々大変なのは分かったけど、症例が入ることを見込んで選んでいないにも関わらず「症例の進捗はどうなっている?」とか聞いてくる依頼者さんは何なのかな?
無茶ぶりじゃないですか、依頼者のりすさん?
依頼者として意識しておきたいこと(依頼者のりす)
これについては、依頼者の中で”症例数を稼げる見込みがあって入れた施設”と”それ以外の関係性のために入れた施設”を整理して戦略を練っていくことが重要だと思ってるよ。
そして、それがあまりできていないからCRO側との摩擦が生じてしまっているのではないかと思っている。
立場的にCROに対して”この施設は先生との関係性もあって入れた施設ですよ”とは言いにくいので(変な形で先生の耳に入ったらトラブルになるので)、症例数を稼げる見込みで入れた施設について「この施設では症例数をしっかり確保したい」ということを共有して重点的に対策を練る方が効果的かなと。
 のりす
のりす もちろん、症例を稼げる見込みで入れた施設でも想定以下しか組み入れられないこともあるので、そのリスクヘッジとして”関係性重視で選んだ施設”についても対策を考えていく感じです。
でも残念ながら、私の会社にいる人たちを見渡してみるとこの辺りの整理をせずにCROに症例が入らない理由をひたすら聞いている人たちもいるのだよね…
なので、依頼者側の意識としても改善の余地が大きいかなと感じる今日この頃なわけですね。
まとめ
今回の記事では、依頼者が選んだ治験実施施設についての不満をテーマにお話をしていきました。
お話したこと以外には、症例を稼げる見込みで入れた施設にも関わらず実際には症例が全然入らないという施設も入ってくるわけですが、ここはなかなか難しいところです。
なぜなら、Feasibilityの時に先生が「この条件であれば症例はたくさん入る」と言っていても結構な確率で実際にはそれほど入らないですからね。
私たちがカルテスクリーニングをしても良いということあればもう少し正確な症例数の見積もりはできそうですが、現実的には公開されている情報からその施設の適格症例数を見積もることはかなり困難ですよね。
もし、依頼者側で組んだアルゴリズムに沿ってFeasibilityの段階で施設が具体的な数字を出してくれれば良いのですが、それもなかなかハードルが高いのですよね。
ドラッグラグ&ロス解消に向けて色々と議論されていますが、実はこのFeasibilityの段階での症例数の見積もり精度の向上というのも大事な議論な気がしているのでこの辺りのテーマも是非活発に業界の中で議論したいところかなと感じています。



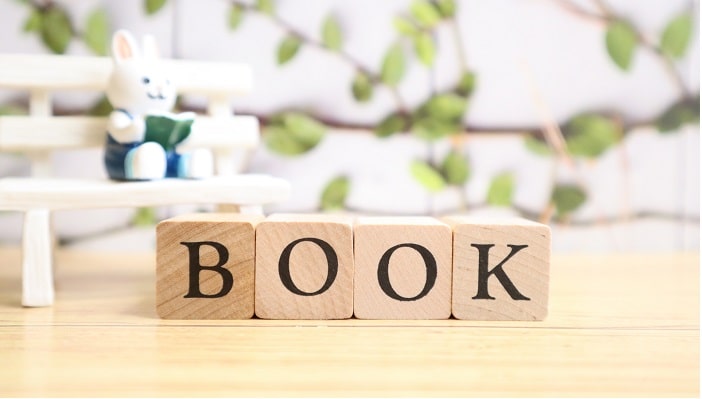
がついに始動!.jpg)

